「ほら見て。高耶さん。このはなびらはまるで練り絹のようでしょう?しっとりと滑らかで肉厚でおもみがあって……ひんやりしてる。きっと熱を吸い取ってくれますよ。待っていて……今ラクにしてあげる」
水に落ちた犬のように高耶がぶるりと大きく震えた。
直江がそのシフォンのような花弁を高耶に埋め込んでいく。
充血し熱を孕んだ粘膜にひやりとしたすべらかな感触がしのびこむ。表面の酒精が沁みて、むず痒いような痛みが走る。
受けている仕打ちの恥ずかしさとそれを拒めない自らの浅ましさに耐え切れずに、ついに高耶が嗚咽を洩らし始めた。
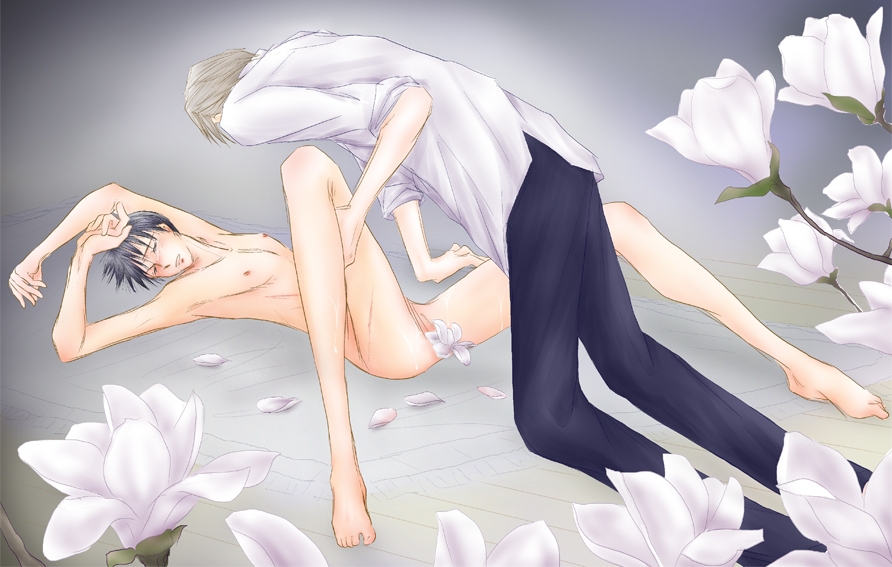
裏庭TOPへ